腸内フローラとは/
酵素と発酵食品
腸内フローラとは

人間の腸内には5000種類以上、100兆個にも及ぶ様々な細菌・微生物が生きています。腸内の細菌・微生物を顕微鏡で観ると、腸内に色とりどりの花が咲くお花畑のようであることから、腸内のお花畑(flora)で「腸内フローラ」と名付けられました。
腸内フローラの環境と
バランス
腸内環境が悪い場合(悪玉菌が多い場合)、便の状態からも推測されます。便が硬くコロコロした状態や便の色が黒く、臭いが悪いときは腸内環境のバランスが崩れていると言えます。
腸内環境を整えるには
「善玉菌」を増やし、「悪玉菌」を減らす必要があります。
「悪玉菌」を減らすためには、規則正しいストレスのない生活と食生活の見直しを行う「腸活」が重要です。be my floraでは、理想的な食生活として、久司道夫先生の「マクロビオティック理論」をおすすめしています。悪玉菌は、アルカリ性環境を好み、酸性環境では死滅する性質があるため、酢酸で腸内を酸性にする事で「悪玉菌」を減らすことが可能と言われています。
そして、「善玉菌」を増やす事も大切です。植物性タンパク質、食物繊維、ミネラル、ビタミンを豊富に含む食事や、オリゴ糖や発酵食品などは善玉菌の大好物です。発酵食品に含まれる豊富な微生物は、善玉菌のエサとなり、善玉菌を活性化させます。
- ◆善玉菌…健康に有益な菌の総称です。体に良い働きをし、有害物質を対外に排出するのを助ける作用します。
- ◆悪玉菌…腸内のタンパク質を腐敗させ有害物質を作り、便秘や下痢、肌荒れ、アレルギーを引き起こす原因になると言われています。
- ◆日和見菌…善玉菌と悪玉菌のバランスにより働きが変わります。優勢の方に味方するため、「腸内フローラ」を整える事が大切です。
腸内フローラとビーマイフローラ
腸内フローラの環境を整えるのにビーマイフローラはとても良いパートナーの様な関係と言えます。ビーマイフローラの発酵成分が腸内フローラを整え、善玉菌の多い環境に整えてくれるお手伝いをしてくれるのです。腸内フローラが整うとまず1番に体感するのはデオドラント効果と言えます。腸内フローラが整うと、良い事ばかり、免疫力UP・美容効果・ダイエット効果・デオドラント効果等、沢山の恩恵が得られます。 ※ 人により効果の違いがあります。
悪玉菌のこわい働き
加齢、ストレス、食べ過ぎ、白砂糖、
動物性タンパク質、喫煙、飲酒
悪く、
悪玉菌優勢に
どんよりとして
老けて見られ、
むくみや肥満、
あらゆる生活習慣病、
病気を誘発 必要な栄養分
(サプリや薬も)
が吸収されず、
エネルギー代謝の
低い冷え性体質に
体内で大量発生。
痛んだ細胞が
放置され、やがて
がん細胞などへ 退愛に不純物が
堆積、腐敗して、
便秘や体臭の原因に。
肝臓や腎臓の
負担も増大
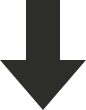
善玉菌の嬉しい働き
be my flora を飲む
善玉菌優勢に
食欲旺盛でも
ベスト体重を維持 体に必要な
栄養の消化吸収や
エネルギーの
代謝がアップ
活性酵素の
影響も少なく、
細胞から元気。
お肌もピカピカ 体内の老廃物の
排泄や有害物質の
解毒が速やか。
便秘しらず、
病気しらずに





